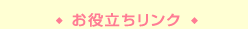近 視
近眼ってどんな眼
近視(近眼)とは近くの大きなものしか見えない目ではなく、近くにピントが合った目のことです。
たしかに遠くは見えにくいので、「視力が悪い」という印象がありますが、矯正視力さえ良好なら、むしろ「近くが良く見える目」なのです。
光学的には図に示すように「無限遠からの平行光線(点線)が網膜の前方で焦点を結ぶ状態」と考えられます。
また、眼球の長さに対して、目の屈折力が強すぎるとも言えます。すなわち眼球の長さが普通で目の屈折力が強すぎる状態の「屈折性近視」と、眼の屈折力が普通で眼球が長すぎる状態の「軸性近視」の二種類があります。
いずれにせよ、近視は、いわば近くにピントを合わせたカメラの状態であり、近くを楽に、はっきり見ることができます(実線)。
100メートル先にある物陰がウサギなのか狼なのかを判断しなければ生き延びて行けない大昔とは異なり、長時間活字やコンピュータなど近くを見ることが多い現代人にとっては、むしろ有利な目ともいえます。
つまり正視や遠視の人(次回詳しくご説明します)は、根を詰めて一生懸命がんばらなければ近方の細かいものを見続けることは出来ませんが、近視の人はもともとの眼球の構造上、何の努力もなしに楽に近見をこなすことが出来るのです。
しかし、黒板の字が見えない、道路標識がわからないなど不便な点もあります。眼鏡、コンタクトはこの不便さを補う道具です。したがって、不便を感じなければ使う必要はなく、むしろ近くを見るときには裸眼の方が良いぐらいです。
ここで、裸眼視力がいくら以下という問題ではなく、ピントの合う位置が16cm以内のような強度近視は、ほとんどが強い「軸性近視」であり、眼球が伸びて薄くなっています。
その結果、網膜はく離や網膜出血などさまざまな目の病気を起こしやすくなっています。このような近視の人は、眼科で定期検査を受ける必要がありますので注意してください。
近眼は老眼にならないの?
目に入ってきた光は、角膜(カメラのフィルター)、水晶体(カメラのレンズ)を通って屈折され、眼球の奥にある網膜(カメラのフィルム)に到達して像を結びます。
人間の眼は、網膜でピントが合うよう無意識のうちに水晶体の厚さを調節しています。
まるで自動焦点機能つきのカメラのような働きがあるのです。
老化が進むと水晶体の弾力性が弱まり、硬くなって厚みを調節することが出来なくなります。近いところを見る際に十分な水晶体の厚みが得られず、網膜にピントが合いません。これが、老眼と呼ばれる状態です。
さて一般に、近視の人は老眼になるのが遅く、遠視の人は老眼になるのがはやいと言われていますが、この考えは正確ではありません。
近視の人は老眼になっても、正視、遠視の人と比べて、もともと近いところにピントが合っているので、その分だけ水晶体の調節を必要とせず、見かけ上、老眼になっていないようにみえるだけなのです。
特にしっかりと矯正したメガネやコンタクトレンズを装用している近視の方は、全く正視の方とかわらない調節力を必要とし、同じようなペースで老眼(水晶体の老化)は進みます。
実際ピント合わせの能力は10才でもすでに低下を始めており、何才から老化した目だ、とはっきり言えるものではありません。
しかし、60才ごろにはピント合わせの能力は必ずゼロになってしまいます(究極の老眼)。
したがって、無理をして老眼対策を遅らせるより、度数が軽いうちに遠近両用眼鏡のような便利な道具に慣れていく方が賢明なのです。
むしろ老眼によるトラブルの多くは、対策を遅らせすぎて慣れるチャンスを逸したために起きています。無理をしていると目の疲れ、肩こり、頭痛、吐き気のような症状まで現れて来るのが老眼です。過度な我慢をせず、一度眼科医に相談してはいかがでしょうか。
視力回復訓練?
結論から言うと、いわゆる視力回復訓練で近視は治りません。ただ、裸眼視力が良くなることはあるかもしれません。
しかし、裸眼視力には本質的な意味はなく、「矯正視力」こそが本当の意味での視力であることは以前にご説明した通りです。どういうことなのか、視力回復訓練にからめてもう一度わかりやすく説明しましょう。
いわゆる仮性近視(本当は調節痙攣)の場合には、視力回復訓練によって裸眼視力が良くなることがあります。これは近方を見るためにがんばって調節した水晶体の状態が痙攣を起こしたように持続してしまう状態なので、もともとが近視ではない人にも起こる病態だからです。
しかし、調節痙攣の有無は、眼科で点眼薬を用いた試験を行うと簡単に診断が可能ですし、治療も出来ます。逆に調節痙攣ではない近視の場合、治療器や訓練などで近視が減り視力が改善することは決してあり得ません。
要するに訓練しなくても治る眼か、訓練しても意味のない眼かのどちらかなのですから、この世のなかに営利を目的とした視力回復センターが存在すること自体、眼科専門医としては容認できません。また、実際には調節痙攣が学童年令で生じることは稀です。ランドセルを背負って吸い込まれるように通院?している子供たちを見ると、とても切ない思いになります。
ところで、「裸眼視力」とはぼんやり見える状態でどこまで視力表を「当てる」ことができるか、という視力であることもすでにご説明いたしました。したがって、目を細めたり、逆に大きく見開いたりと無理な状態にしても良いか、はっきり判ったものだけ答えるか、勘で答えても良いか、答えるまでの制限時間を設けるかなどによって裸眼視力の値は大きく変動します。
また、慣れてくれば、視力表の視標のぼやけ方などでどちら向きかを「当てる」ことができるようにもなります。
つまり、くり返し視力表を当てる訓練をする事(これを称して視力回復訓練)で「裸眼視力」は良くなり得ます。しかし、これは決して訓練方法や治療器が近視に有効であったわけではなく、悪い視力でも「当てる」勘を養っただけに他なりません。また、裸眼視力が改善しても、目を細めて時間をかけ、ぼやけた視標で判断した視力なのですから、本人の見えにくさが減ったわけでもありません。
結局、周りの友達が1分で読める黒板の文章を、3分も5分もかけて読まされている子共にとっては大変な苦労です。
「訓練でよかった」かのような「怪しげな視力」に喜んで眼鏡をかけさせないでいるのは明らかに親の傲慢に他なりません。
乱 視
乱視は無秩序?
よく間違われることですが、乱視とは、物が二重に見える状態のことではありません。また、いわゆる不正乱視と呼ばれる無秩序な乱視もありますが、これは角膜の外傷や感染による瘢痕などの特殊な状態で形成されたもので、一般的には多くありません。
通常の乱視(正乱視)は、レンズとしての目が完全な球面でない状態を意味します(図①②)。
つまり完全な球面の一部を切り取った状態ではなく、方向によってカーブが違う、ラグビーボールのような曲面を丸く切り取った状態が乱視です。
したがって、乱視の目ではすべての方向のピントを同時に合わせることはできません。例えば、縦方向のピントがあうと横方向のピントがずれ、また逆も然りなのです。
しかし、光学部品として作られるカメラのレンズでも、精密に測れば多少のゆがみ、方向によるカーブの違いが存在します。ましてや人間の目は生き物ですから、乱視があるのは決して異常なことではなく、むしろ当然です。それでも、乱視が強すぎると正確にピントを合わせることが出来なくて、とても疲れてしまいます。
だから、乱視は完全に矯正することが原則です。ただ、乱視の入った眼鏡は、慣れるのに多少の努力が要りますから、最初はわざと弱めに合わせることもあります。
また、近視や遠視とは異なり、乱視用の眼鏡、コンタクトレンズは、度数の他に乱視軸の角度
弱視
弱視とは視力の弱い人?
こどもの目の発達には、絶えずものを見る訓練が必要です。もし、こどもの視力が発達する途中で、絶えずものを見る訓練ができないと、視力の発達は抑えられ、止まってしまいます。これを弱視といいます。たとえ強度の近視で裸眼視力(眼鏡をかけない視力)が0.01であっても、眼鏡をかけると1.0見えるようになる場合には弱視といいません。
このように、弱視はものを見る訓練ができないと起こりますが、ものを見る訓練ができない状態になる原因としては、斜視や遠視が上げられます。
斜視があると両眼視ができないため、ものが二重に見えます。ものが二重に見えると脳が混乱するため、斜視になっている片方の目を使わないようになり、使わない方の目が弱視になる場合があります。これを斜視弱視といいます。
また、遠視があると近くを見る時も遠くを見る時もはっきりと見えないため、視力が発達せず、弱視になる場合があります。これを屈折性弱視といいます。
逆に、近視の場合には近くのものにはピントが合うので、発達途中でものを見るチャンスとしては十分な環境にあり、弱視にはならないのが普通です。
そのほか、生まれつき白内障などの目の病気がある場合、あるいは乳幼児期に眼帯を長い間(3〜7日間程度)つけたりした場合にも、ものを見る訓練ができず、弱視になる場合があります。
斜視と違い、弱視は保護者の方が注意していても分からないことがままあります。特に片方の目だけが弱視の場合、良い方の目で普通に見ているため、気がつかないことが多いようです。弱視は視力の発達が抑えられている期間の長さや程度によって、良くなる場合とならない場合がありますが、3歳くらいまでに見つかると、治る可能性は高くなります。3歳児健診の視力検査を必ず受けるようにしましょう。
弱視を治す方法としては、遠視が原因の場合には、遠視用の眼鏡をかけます。そのほかの場合は、弱視の視力増強訓練を行う必要があります。弱視の視力増強訓練は、遮閉法という方法で行います。遮閉法は、良い方の目を隠すことによって、弱視の目を無理にでも使わせようとする方法です。この方法は、病院「だけではなく、家庭でもずっと行わないと意味がありませんので、家族の協力が必要となります。遮閉法を行うときには眼科医の指示に従いましょう。
また、4歳児以上では視能訓練士(国家資格保持者)による器械を利用した訓練を行います。亀田クリニックには6名の視能訓練士が常勤し、これらの指導を積極的に行っています。
老人性白内障
老人性白内障とはどんな病気?
さて、視力、屈折、調節、弱視と話をすすめてきましたが、ここからは少し疾患(病気)の話をしたいと思います。
人の眼は、よくカメラにたとえられますが、カメラのレンズに相当する働きをするのが水晶体です。水晶体は直径約9ミリ、厚さ約4ミリの凸レンズ状の組織で、その働きには、カメラのレンズと同様に光を集める働きとピントを合わせる働きがあります。
このため人体のなかでも、水晶体の持つ最も大きな特徴は、透明であるということです。光を透過し、眼底の網膜に光を集め、外界の物体の像を結ぶ機能があるからです。透明なはずの水晶体が濁ってくると光が眼底に入る前に散乱されて、網膜に像を結ぶ働きが弱くなり、かすんで見えるようになります。この水晶体の濁った状態を白内障といいます。
白内障の原因はたくさんありますが、最も多いのは加齢によるもので、老人性白内障という名前で呼ばれています。年齢と共に水晶体が白く濁っていくのですが、髪の毛が白くなっていくのと同じ老化現象で、完全に予防することはできません。40歳を越えたほとんどの人は、部分的にせよ水晶体の混濁を生じていますから、ある意味、白内障にかからない人は皆無であるとも言えます。
次に多いのが、糖尿病に合併した白内障です。糖尿病にかかっている人は、白内障になりやすいことが知られています。
その他、ステロイド薬を長い間使っていることによるもの、眼の外傷が原因になるもの、眼の中の他の病気(炎症など)が原因になるもの、生まれつきのもの、アトピー性皮膚炎に合併するものなどがあります。
これら白内障では、症状が進むと、ものがかすんで見えたり、暗くなると見えにくくなりますが、状況によってはむしろまぶしくなったり、一時的に近くが見やすくなるなどの特殊な症状も出ますから注意が必要です。眼の痛みや充血のないのも白内障の特徴です。
白内障の治療には薬物療法と手術療法の二つがあります。薬物療法には点眼薬によるものと内服薬によるものがありますが、一度混濁した水晶体を再度透明に戻す効果はほとんど期待できないのが実態です。
したがって、薬物療法のほとんどは進行を阻止する目的での予防的治療だと認識して下さい。いったん混濁が進行して視力を著しく障害した白内障に対しては、手術療法が唯一の治療方針となります。
白内障にはどういう手術をするのでしょうか?
現在、世界の医療先進国で最も一般的に施行されている白内障手術の術式は「超音波水晶体乳化吸引術および人工レンズ挿入術」とよばれる術式です。亀田クリニックでも年間500件程度の白内障手術が施行されていますが、ほとんどがこの術式によるものです。
水晶体は前嚢、後嚢とよばれる薄いカプセルの中にある皮質と呼ばれるやわらかい部分と核と呼ばれる硬い部分から構成されています。
超音波乳化吸引という方法は、水晶体の核の部分を超音波発信装置によって乳化(細かく破砕)し吸い取ってしまう方法です。初期の白内障手術では水晶体を嚢ごとまとめて取り除くような方法がとられていましたが、眼球にあける切開創がとても大きくなってしまうことと、人工レンズの固定場所がなくなってしまう不具合がありました。
しかし、超音波水晶体乳化吸引術では3ミリ以下の小さな切開創から超音波発信装置を挿入し、硬い核を含めて水晶体を吸引し、しかも後嚢だけを残すことで人工レンズの固定場所を確保することが可能になりました。
ところで、水晶体(学術英語ではレンズ)は眼球における屈折調節の要です。これを吸い取ってしまうと当然ピントが合わなくなります。そこで、もともと水晶体の位置した部分に、人工的なレンズを移植する方法がとられる様になりました。これが人工レンズ挿入術というわけです。これより日常の生活にほとんど不自由のない視力を得ることが可能になりましたが、後嚢の弱い症例や他の眼疾患(網膜症やぶどう膜炎など)を併発しているような症例では、あえて人工レンズを挿入せずにコンタクトレンズなどによる矯正を選択することがあります。
また、人工レンズには自ら変形して調節を行う能力(遠方から近方まで連続してピントをあわせる能力)はないので残余する乱視とともに眼鏡による補正がほとんどの場合必要になります。したがって、白内障の手術を行っても眼鏡いらずになるわけではありません。
一度白内障の手術を施行すれば二度と白内障にはならないというのは本当です。ところが誤解を招きやすい病名に「術後後発白内障」というものがあります。これは挿入された人工レンズに眼内の細胞成分が付着し線維化した皮膜を形成してレンズがよごれてくる現象です。また、白内障になったと心配される方がいますが、レーザー光線を利用してレンズを元通りのきれいな状態に戻せますのであまり心配はいりません。
緑内障
緑内障は眼圧が高い?
目の中には常に房水とよばれる液体が流れています。房水は毛様体でつくられ、シュレム管から排出されます。目の形は、この房水圧によって保たれ、これを眼圧とよびます。
緑内障は、何らかの原因で視神経が障害され、視野(見える範囲)が狭くなる病気ですが、眼圧の上昇がその病因の一つと言われています。
緑内障は、眼圧が高くなる原因によって、主に
①原発開放隅角緑内障(房水の出口が徐々に目詰まりし、眼圧が上昇していく慢性の病気)
②原発閉塞隅角緑内障 (隅角が狭くなり、ふさがって房水の流れが妨げられ、眼圧が上昇。慢性型と急性型がある。)
③先天緑内障 (生まれつき隅角が未発達であることからおこる緑内障)
④続発緑内障 (外傷、角膜の病気、網膜剥離、目の炎症など、他の目の疾患や、ステロイドホルモン剤などの薬剤によっておこる緑内障)
に分けられます。いずれにせよ眼圧の上昇が緑内障の基本的な病態であると考えられてきました。
ところが、開放隅角緑内障のひとつに、眼圧が正常範囲(10〜20mmHg)である正常眼圧緑内障があります。
近年行われた全国的な調査の結果からは、なんと緑内障の約6割が正常眼圧緑内障であることがわかりました。眼圧の上昇は緑内障の病因の一つであることは確かですが、成人病検診などで眼圧が正常値でも決して安心は出来ないというのが正直なところです。
しかも、急性の緑内障を除き、一般的に緑内障では自覚症状はほとんどなく、知らないうちに病気が進行していきます。視神経の障害はゆっくりとおこり、視野(見える範囲)も少しずつ狭くなっていくため、目に異常を感じることはありません。
結局のところ手前味噌になりますが、眼圧の変動や眼底の視神経乳頭の状態を専門医(眼科医)が総合的に判断してはじめて診断を下せるのが、緑内障であるといわざるを得ません。亀田総合病院でも、折に触れて眼圧検査や眼底検査を施行している理由のひとつには、緑内障のスクリーニング(ふるい分け)の意味合いがあるのです。
網膜症
高血糖がなぜ悪い?
(糖尿病)
糖尿病患者は現在全国で500万人以上いるといわれ、その数は今なお急増しています。糖尿病は発病初期にほとんど自覚症状がないため軽視されがちですが、全身に及ぶ合併症をひきおこす油断できない病気です。特に「三大合併症」と言われる「糖尿病網膜症」「糖尿病腎症」「糖尿病神経障害」は、発症頻度の高い重大な慢性疾患です。
それでは、どうして血糖の高い状態が体に悪さをするのでしょう。ひとえにそれは、体中の毛細血管に悪さをするから、と理解してください。実は「網膜症」も「腎症」も「神経障害」も、すべて生命代謝の根幹であるところの毛細血管の循環が極端に悪くなるから起こるのです。
たとえば目の奥には、網膜というカメラのフィルムにあたる重要な膜があり、ここには多くの毛細血管が分布しています。
糖尿病の方の血液は、糖分を多くふくみ、粘性も高いため、毛細血管を詰まらせたり血管壁に負担をかけたりして、最終的に毛細血管網の破綻が生じます。
そのため、網膜に酸素や栄養が不足し、眼底出血や硝子体出血などの症状を示す「網膜症」へと進展するのです。腎症や神経症についても同様な機序で病気が進行します。
ところで、糖尿病の診断がつくと必ず内科の先生方は患者さまに眼科受診を勧めます。内科の先生が目の病気を心配してくださっているのには違いありませんが、実はもうひとつ大きな理由があるのです。
人間の網膜(眼底)は、「唯一」生理的な状態で血管を透見することが出来る組織なのです。つまり、なんら組織を障害することなく生の血管の状態を把握できる生体唯一の覗き窓なのです。
したがって、血管の病気ともいえる糖尿病がどの程度を蝕んでいるかを推測するうえで、最も簡単かつ直接的に観察できる手段が眼底検査なのです。糖尿病のほか、高血圧や動脈硬化なども眼底の血管を見るだけで、ある程度病状の進行が推察できます。また、眼底検査から逆に病気の存在が見つかることも多々あります。
国民保健衛生の状況が高齢化、欧米化の一途を辿るなか、これら血管の障害をもととする病気も増える一方です。
眼科における眼底検査の重要性もここにあることは、是非皆様にもご承知頂きたいところです。
硝子体
眼の中に蚊がいる?
水晶体(白内障になる部分)や網膜という言葉は雑誌や新聞などでよく目にしますが、硝子体という言葉は比較的なじみが少ないのではないでしょうか。
ちなみに硝子体というとガラスの様にとても硬そうな語感がありますが、実際には生の卵白のようなゲル状の物質です。
ところでこの硝子体、若い頃は眼内一杯に充満して一様な状態を保っています。しかし、年齢が進むにしたがって、徐々に粘りのあるゲルの状態から液化して水のような状態に変化します。
すると、液化の進んだ水の部分とゲルのままの部分とに分離して、一様性がなくなってきます。つまり光学的な濁りを生じてきます。
このような状態になると、特に後部の硝子体(視神経乳頭に近い部分)は眼球の内壁(網膜)から剥がれやすくなり、後部硝子体剥離という状態を生じてきます。
すると、さらに光学的な濁りが増して人によっては飛蚊症(ひぶんしょう)を自覚的するようになります。まるで目の前に蚊が飛んでいるように見えますが実際には目の中に蚊のような濁りが生じているのです。したがって、飛蚊症は病気とは言い難い老化現象です。
硝子体の病気
前回は硝子体の構造と加齢についてお話しました。特に40歳後半以降良く見られる飛蚊症は、加齢による硝子体の変化である後部硝子体剥離によって生じるもので、病的ではないことを付け加えました。
しかし、飛蚊症を前駆症状として発生する本当の意味での硝子体の病気が、頻度は少ないもののいくつかあります。
最も注意したいのが網膜剥離です。硝子体が網膜から剥がれる時に、本来は剥がれるはずのない網膜までが一緒に剥がれてしまう病気が網膜剥離です。
したがって、後部硝子体剥離に伴う飛蚊症が先駆し、追って網膜剥離の症状が顕在化してきます。飛蚊症が単に後部硝子体剥離だけで生じているのか、網膜剥離を伴っているのかは、眼底の検査を行えばすぐに分かります。
その他、後部硝子体剥離に伴って網膜の一部がちぎれ出血を起こす硝子体出血や、特殊な炎症であるぶどう膜炎でも硝子体が混濁し、強い飛蚊症を生じます。
いずれの場合でも、正常な老化現象である後部硝子体剥離だけであるのか否かが、その後の経過を大きく左右します。
時には早期の硝子体手術が必要であったり薬物治療が有効であったりしますから、とくに新たな飛蚊症、あるいは今までと違った飛蚊症を自覚したときには迷わず眼科医に相談してください。
人工網膜
ここ数年の眼科学の進歩は目覚しく、これまで救うことの出来なかった多くの疾患も治療が出来るようになりました。
しかし、不幸にして大きな事故や重症な遺伝性疾患などによって光覚(光を感じる能力)を失ってしまったような方に対する決定的な治療法は現在のところ見出されていません。
だからといって眼科医や研究者もだまって手をこまねいているわけではありません。今までの概念とは全く異なった角度から視覚障害に立ち向かおうと研究努力を積み重ねています。そのひとつが人工視覚器の開発利用です。中でも人工網膜の開発は最も現実味をおびつつある人工視覚器のひとつです。
人間の正常な視覚機能を極端に簡略化して説明すると、外界から照射された光刺激を網膜が電気刺激に変換し、その電気を視神経が脳の視覚中枢に伝達して認識が行われる」ということになります。
もし網膜に広範な変性症や外傷などの致命的な機能障害が生じると光を受け取っても網膜が電気を発生しなくなります。したがって、脳では何ら視覚刺激に伴う信号を受け取ることがなくなって、盲になってしまう訳です。
ところで、エレクトロニクスの進歩も目覚しく、光線が当たるとわずかながら電気を発生する厚さ数十ミクロン、直径1〜2 ミリの特殊な円盤が開発されています。
そこで、この円盤を網膜の裏側に埋め込む手術を行い、長期間にわたって毒性や拒絶反応を生じることなく、光の刺激に対して電気を発生し続けるか、という臨床試験が実際に人の眼で行われています。
さらに最近では眼球そのものを失ってしまった(眼球摘出を受けた)方の脳に電極を埋め込み直接「脳の視覚中枢」を電気的に刺激することによって大まかな形の認識が可能であったという報告も出ています。
いずれ、そう遠くない将来にこれら画期的な医療材料の恩恵に与れる日が来るものと確信しています。